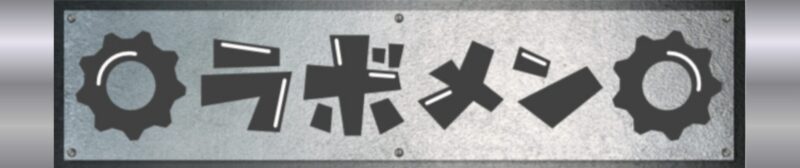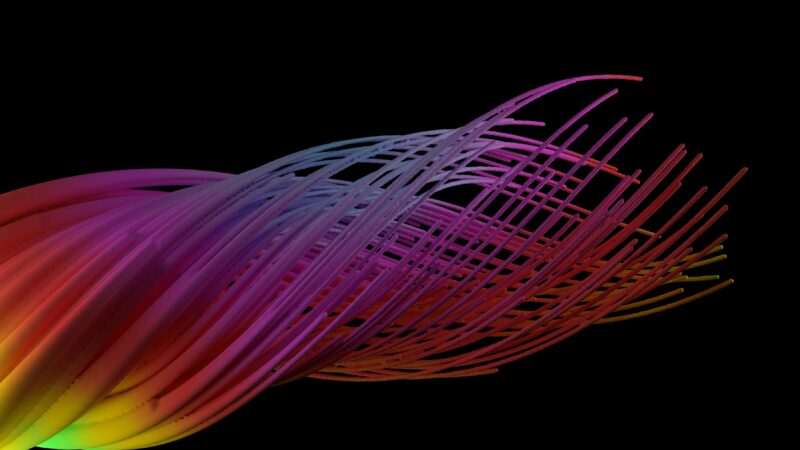インクルーシブカルチャーブランドで拓く新しい働き方と表現の場
障がいのある人や困難を抱える人にとって、自分らしく働きながら自分らしく表現する場所はまだ多くありません。
そんな現状を変えようと誕生したのが、2025年秋にスタートした インクルーシブカルチャーブランド「irotoa(イロトア)」 です。
横浜市の就労継続支援B型事業所 ラボメン は、このブランドと協力し、利用者たちがクリエーターとして社会とつながるモデルを構築しています。
本記事では、ブランド誕生の背景からラボメンとの連携、専属クリエーター Tisato さんの契約に至るまでの経緯、創作活動の裏側、社会的意義、そして今後の展望までをできる限り詳しくまとめました。

上の画像は、irotoaが掲げる「個性の色、命の音」をイメージしたアブストラクトアートです。
色と音の波が絡み合い、個人の多様な表現が響き合う様子を象徴しています。
irotoa誕生の背景とコンセプト誕生の背景
irotoaは2025年9月1日、東京・原宿にある神宮前3丁目に 「irotoaコラボレーションストア」 をオープンしました。
運営元の株式会社太洋光芒は、横浜で就労継続支援B型事業所 COLORS弘明寺 を手掛ける企業であり、福祉と文化をつなぐ新しい拠点としてこのブランドを立ち上げました。
表現活動を通じて社会参画の機会を増やすことを目的とし、福祉の枠にとらわれない経済活動を目指しています。
理念と目的
ブランド名の“irotoa”は、「色(iro)」と「音(oto)」に「a」を掛け合わせた造語で、「個性の色、命の音」という意味を込めています。
この言葉には、障がいの有無に関係なく一人ひとりの感性や経験が色彩や音となって表れ、それらが重なり合うことで文化を豊かにするという願いが込められています。
福祉製品にありがちなチャリティー的な扱いではなく、デザイン性や品質にこだわった一般商品として市場で評価されることを重視しています。
4つの自立を支える仕組み
irotoaでは、利用者が自己表現だけでなく就労や生活の自立も進められるよう、次の4つの柱を用意しています。
表現の自立:一人ひとりのテーマや関わり方を尊重し、店舗やオンラインで作品を発表する場を設ける。
社会的自立:店舗運営や接客、販売補助などの実務を通じ、仲間と共に働く経験を積む。
生活の自立:個々のペースに合わせた働き方や時間設計、適切な賃金で安心して働ける環境を整える。
経済的自立:作品や商品の販売を通じて収入を得る機会をつくり、活動を継続できる仕組みを作る。
これらの仕組みによって、単に作業を提供するだけの福祉施設ではなく、表現とビジネスが両立する場を作り出しています。
ラボメンがirotoaに参画 – 5つの架け橋
ラボメンは「好きなことを仕事に近づける」を理念に、オリジナルグッズの制作やアート作品制作、PCデータ入力などさまざまな活動を提供してきた就労継続支援B型事業所です。
2025年秋、ラボメンはirotoaのブランドメンバー “irotoanista(イロトアニスタ)” として正式に参画し、新しいアートシリーズ 「彩音戯画(カラートーンアート)」 を発表しました。
このシリーズでは、次の5つの橋を架けることを目指しています。
個性の色をつなぐ
ラボメン利用者の作品には、それぞれの人生経験や日常の風景が色彩となって表れます。
作品は純粋な模倣ではなく、作者自身の記憶や体験が反映された「生きた表現」であり、その個性を多くの人々と共有する場としてirotoaが存在します。
命の音を重ねる
制作現場には、筆がキャンバスを走る音やミシンのリズム、仲間の笑い声が常に響き合っています。
作品づくりの過程そのものが「命の音」となり、完成した作品からはそのエネルギーと躍動感を感じ取ることができます。
福祉とカルチャーを結ぶ
irotoaでは、福祉施設で制作された作品を慈善的な「福祉商品の枠」で扱うのではなく、デザイン性や品質によって評価される一般商品として販売します。
福祉とカルチャーの横断によって、障がいの有無に関係なく創作物が市場で正当な価値を持つことを目指しています。
利用者からクリエーターへ
参画したアーティストたちは「福祉施設の利用者」という肩書きを越え、ブランドメンバー irotoanista として作品制作に携わります。
これにより、自分の作品が社会的に認められ、クリエーターとしての自信を育んでいます。
一点物の価値を世界へ
作品の多くは、筆の滲みや偶然生まれた模様が混ざり合い、同じものが二つとない一点物です。
所有者は「自分だけの作品」を持つ喜びを味わい、その価値を世界に伝える役割も担っています。
プロダクトとサービス – 彩音戯画と笑み咲か達磨
彩音戯画の概要
彩音戯画は、ラボメンとirotoaが共に開発したアートプロダクトシリーズです。
利用者が描いたアート作品をキャンバスやグッズに展開し、デザイン性の高い商品として展開しています。
作品は、日常生活の風景や記憶をモチーフにしたカラフルな図柄が特徴で、見た人の気持ちを明るくするような色づかいが魅力です。
新商品「笑み咲か達磨」の特徴
彩音戯画の新ラインアップとして発表された 「笑み咲か達磨(えみさかだるま)」 は、伝統的な達磨にポップな色や模様を施した縁起物です。
福祉施設の利用者が描いたパーツを組み合わせ、ひとつとして同じ柄がない一点物になっています。
新しい年に笑顔が咲き、願いが叶うようにとの思いが込められています。
発売直後から縁起物としてだけでなくインテリアアートとしても人気を集めています。
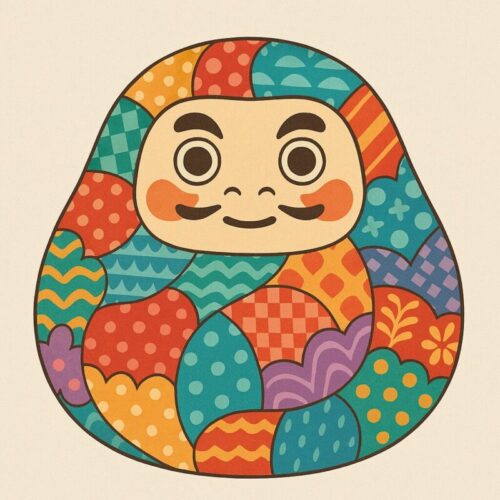
彩音戯画の一部として登場した「笑み咲か達磨」をイメージしたイラスト。
様々な模様とカラーが組み合わさり、ひとつとして同じものがない個性を表現しています。
商品概要(彩音戯画/笑み咲か達磨)
以下の表は、プレスリリースで公表された彩音戯画シリーズおよび笑み咲か達磨の販売概要をまとめたものです。表の内容は公的情報に基づき、必要最低限の項目のみを記載しています。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2025年9月1日 |
| 予約開始 | 2025年8月下旬より(数量限定) |
| 販売場所 | 原宿・神宮前3-25-18 「irotoaコラボレーションストア」および公式オンラインストア |
| アクセス | JR原宿駅から徒歩約5分、東京メトロ明治神宮前〈原宿〉駅から徒歩約4分 |
| お問い合わせ | COLORS(ラボメン)専用窓口:045-264-7727 |
専属クリエーターTisato – 契約と挑戦
契約に至る経緯
ラボメンのデザイナー兼アーティスト Tisato(チサト) さんは、カラフルで幾何学的な絵画を得意とし、多くの利用者から憧れの存在でした。
2025年9月上旬、Tisatoさんはオープン準備中の原宿店舗を訪れ、 irotoaの世界観を描いたコンセプト画を代表の塚本さんに贈りました。
この作品が店内で話題となり、来店者からの反響も大きかったため、同月中旬には業務委託契約が締結されました。
この契約は、就労継続支援B型の利用者が一般企業と直接商業契約を結んだ初めての例として、大きな注目を集めました。
Tisatoの役割
契約後、Tisatoさんは以下のような役割を担っています。
・デザイン担当として彩音戯画を牽引 – 彩音戯画シリーズやアクセサリーの原画を描き、商品化のためのアートディレクションを行います。
・作品展示・販売 – 原宿ストアに常設された作品コーナーで原画を展示し、購入者は一点物のアートとして持ち帰ることができます。
・ワークショップやライブペイントへの参加 – irotoa主催のイベントでライブペイントやトークセッションを行い、表現活動の楽しさやプロの視点を伝えています。
ワークショップとライブ制作
ワークショップでは、参加者が色や模様を自由に組み合わせてオリジナル作品を制作します。
Tisatoさんがその場で描くライブペイントを通じて、即興性と緻密さが共存する制作プロセスを体験でき、参加者は創作の楽しさと難しさを同時に味わえます。
イベントは定員制で安全に配慮しつつ開催され、今後はオンライン配信や地方開催も検討されています。
創作と訓練 – アートは日々の積み重ね
日常が創作の源
irotoaとラボメンのアート作品は、障がいゆえの“特別な感性”から生まれるものではなく、日々の経験や訓練の積み重ねから生まれるものです。
メディアは、アートが障がいの産物だと誤解することがありますが、記事では「作品は日常生活の風景や記憶から生まれるもので、身体・認知機能のトレーニングや反復作業を通じた努力の結果である」と強調しています。
この考え方は、作品の価値を福祉ではなくアートとして評価する上で重要な視点です。
訓練と技術の育成
ラボメンでは、絵画や手工芸の技術を高めるための訓練プログラムがあり、利用者が継続的にスキルを磨いています。
筆の使い方、配色理論、デジタルツールの活用、細かな手先の訓練など、専門家のアドバイスを受けながら習熟度を高めています。
また、PCデータ入力やEC運営など事務系の訓練も行い、作家活動以外の仕事でも社会に貢献できる幅を広げています。
代表松橋健太の想い – 共創と家族への思い
家族から生まれた事業
ラボメンの代表 松橋健太 氏は4児の父親で、そのうち2人の息子が発達障がいを持っています。
息子たちが大人になったときに自分の好きなことを仕事にできる環境を作りたいと考えたことが、ラボメン設立の出発点でした。
彼は「支援者」としてではなく、自身もアーティストとして利用者と同じ目線で作品づくりに参加しています。
その姿勢が、施設全体に共創の雰囲気をもたらし、利用者が対等なパートナーとして活躍できる土台となっています。
利用者と共に働く哲学
松橋氏は「支援ではなく共創」を理念に掲げています。
彼は、利用者に“作業”を与えるのではなく、一緒に作り上げる仲間として作品制作や店舗運営に携わります。
これにより、利用者も自然に自分の役割を見つけ、責任感を持って取り組むようになります。
また、彼自身も新しい表現の可能性に挑戦し続けており、その姿は利用者にとって身近なロールモデルとなっています。
社会的意義と未来 – 障がいとカルチャーの交差点
評価軸の転換
irotoaとラボメンが取り組む最大の意義は、作品の価値を「福祉的な善行」から「市場が評価するクオリティ」へと転換することです。
プレス記事では、障害福祉の枠ではなく、デザインと品質で評価される商品を作ることが強調されており、この転換が障がいのある人の働き方を大きく変える可能性を持つと指摘されています。
進化する就労支援
ラボメンでは単純な軽作業に止まらず、デザインやマーケティング、接客など多様な仕事に挑戦できる環境を整えています。
商品化によって得られる収入に加え、利用者自身がブランド運営に関わることで社会で必要とされるスキルを身に付けています。
今後は専門スキルの習得と収入向上を両立させる仕組みが求められています。
地域と全国への展開
プレス記事では、「Harajuku発の試みを、地域の福祉施設や全国へ広げる」という将来的な計画も示されています。
地方の障がい者施設やアートイベントと連携し、各地の文化と福祉が交差するような取り組みが期待されます。
支援の質を保ちながら拡大を続けるためには、現場のノウハウを共有するネットワークづくりが鍵となります。
今後の展望 – 広がる可能性
作品バリエーションと技術の拡大
ラボメンでは、アクリル画やペン画に加え、レジンアクセサリーやデジタルアート など新しい技法にも挑戦する計画です。
プロのアクセサリーブランド「MATERIAL CROWN」とのコラボレーションにより、ハイエンドなジュエリーへの展開も検討されています。
販売チャネルの多様化
今後は、原宿の店舗や公式オンラインストアに加え、百貨店でのポップアップや地方イベントへの出展、ECサイトの多言語化による海外販売、他の就労支援施設との共同販売など、販路の拡大を目指します。
また、購入者が作品に込められた背景を理解できるよう、商品の裏にクリエーターのプロフィールや制作ストーリーを添える工夫も進んでいます。
クリエーター育成と共創コミュニティ
ラボメンとirotoaは、利用者がアーティストやデザイナーとして活躍できるよう、ワークショップやAIツールを活用した制作支援、マーケティングの実践的研修 など教育プログラムを充実させています。
地域のアーティストや企業、学校と協力し、障がいの有無に関わらず共に学び、共に創造するコミュニティを広げていくことが目標です。
おわりに – 福祉とカルチャーの垣根を越えて
ラボメンとirotoaの取り組みは、「福祉製品=慈善」から「デザインと表現によって価値を生み出す」場への転換を示しています。
利用者がクリエーターとして認知され、専門ブランドと契約を結び、作品が一般市場で評価される。
こうした流れは、障がいのある人が自分の得意分野で社会とつながり、経済的自立を果たす新しい道を開いています。
このブログでは今後も、作品の制作秘話やイベントの様子、クリエーターたちの成長ストーリーをお届けします。
個性の色と命の音が響き合う現場から生まれる新しい文化と働き方の可能性を、共に見守っていきましょう。